国内農業は崩壊寸前!?食料自給率38%が示す未来への警鐘
今日の日本は、超高齢社会の進行と少子化の加速に直面しています。
これらがもたらす影響は、単なる労働力不足に留まらず、日本の食料安全保障にまで及んでいます。
現在の日本の食料自給率はわずか38%と、極めて低い水準にあります。
これは、食料の大部分を海外からの輸入に依存していることを意味し、国際情勢の変動や円安の進行が、私たちの食卓を直接的に脅かす事態につながっています。
昨今の急激な円安やウクライナ情勢による国際物流の混乱は、食品価格の高騰を招いており、信用調査会社の調べによれば、平均で12%もの値上げが進行しているとされています。
過去の歴史を振り返れば、第二次世界大戦末期から終戦直後の食糧難は、輸送路の遮断による食料輸入の停止が主要因でした。
今日の日本が、かつてのような食料危機に直面しないと断言できるでしょうか?
食料輸出国であるカナダ(233%)やオーストラリア(169%)はもとより、フランス(131%)やアメリカ(121%)といった欧米の平均的な国々と比較しても、日本の食料自給率の異常な低さは際立っています。
この状況が続けば、有事の際には国家としての存続が危ぶまれる可能性さえあります。
耕作放棄地の拡大と農業従事者の高齢化:見過ごせない国内農業の現実
食料自給率の低さに加え、国内の農業が抱えるもう一つの深刻な問題は、耕作放棄地の拡大と農業従事者の高齢化です。
農林水産省の統計によると、2020年には約437万ヘクタールの耕地面積のうち、8.7%にあたる38万ヘクタールが利用されずに放置されていました。
これは埼玉県全体の面積に匹敵する広さです。
耕作放棄地の増加は、単なる資源の無駄遣いに留まりません。
水田は本来、保水機能を持つことで洪水を防ぎ、地下水を豊かにする役割を担っています。
また、多様な生物を育み、日本の原風景ともいえる田園風景を形成することで、人々に心の安らぎを提供してきました。
耕作放棄が進むことは、これらの金銭には換えがたい国土の価値が失われることを意味します。
さらに、農業を支える人材も急速に減少しています。2021年時点で自営農業に従事する人は約130万人。その平均年齢は約68歳に達しています。
新規就農者の数は年間5万人強いるものの、この7年間で実に45万5,000人もの農業従事者が減少しました。
現在のペースが続けば、約20年後には国内から農業従事者がいなくなってしまうという危機的な状況にあります。
日本の農業は、まさに「崩壊寸前」と呼ぶにふさわしい状況にあると言えるでしょう。
大量輸入・販売がもたらす国内農業への打撃:トマトが語る市場の論理
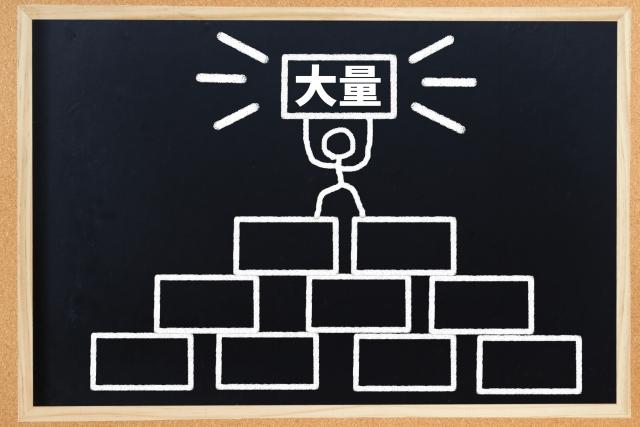
なぜ、これほどまでに国内農業が疲弊しているにもかかわらず、日本は食料の大部分を海外からの輸入に依存しているのでしょうか。
その背景には、現代の大量生産・大量輸送・大量販売に依存した食料供給の仕組みがあります。
例えば、スーパーで手軽に手に入るトマトを考えてみましょう。
食品加工会社は、多数の農家から大量のトマトを買い集め、パック詰めやジュースなどの加工食品へと変えていきます。
こうして大量生産された商品は、全国チェーンのスーパーへと大量に輸送され、消費者の手に渡ります。
この仕組みの中で、全国規模で展開するスーパーは、個別の農家と比較して圧倒的な事業規模を誇り、市場価格の決定権を握っています。
結果として、外国産のトマトの方が安価であれば、スーパーはためらうことなく輸入品を陳列します。
現在、市場に出回るトマトの約45%は輸入品です。
このような輸入圧力にさらされ、加工原料用トマトを国内で生産する農家は、1980年には2万5,000戸存在しましたが、輸入自由化に伴い、現在では約5,000戸にまで激減してしまいました。
価格競争の論理が、国内の農業生産者を次々と淘汰している現実があるのです。
国連が提唱する「家族農業の10年」:持続可能な食料供給への転換
日本政府は、国内の農産物が価格的に輸入品に対抗できないため、農地の大規模化が必要であるという見解を示すことがあります。
しかし、国際社会は全く逆の方向を目指しています。
2017年の国連総会では、2019年から2028年までを「国連・家族農業の10年」とすることが全会一致で可決されました。
家族農業とは、家族の労働力を中心とした農業形態を指し、世界の約5億7,000万ある農場のうち5億以上を占め、世界の食料の80%以上を供給しています。
驚くべきは、家族農業が大規模農業よりもはるかに資源効率に優れている点です。世界の農業資源(土地、水、化石燃料)のわずか25%を利用するだけで、世界の食料の80%以上を生産できるのです。
一方で、大規模農業は農業資源の75%を消費しながら、食料供給は20%以下に過ぎません。
さらに、大規模農業で生産された食料の3分の1は、長距離・長期間の輸送・流通過程で有効利用されずに廃棄されています。
土地の生産性においても、家族農業の優位性は明らかです。日本では農地1ヘクタールで約10人を養えるのに対し、大規模農業が主流のアメリカでは0.9人、オーストラリアでは0.1人しか養えていません。
大規模農業は小麦などの単一作物栽培が中心であるため、干ばつ、洪水、ハリケーン、病害虫などによる大規模な被害のリスクが高まります。
近年、国際的な自由市場の拡大により、少数の食料輸出国が多数の輸入国に食料を供給しているため、特定の輸出国が被害を受けると、国際市場価格が跳ね上がるという脆弱性も露呈しています。
また、アメリカやカナダでは、大量生産での生産性向上のために、発ガン性が疑われている農薬「グリホサート」が使用されています。
日本の学校給食パンにおいても、輸入小麦を使用した製品の多くからグリホサートが検出される一方で、国産小麦を使った製品からは検出されていません。
価格だけを見れば、国際的な大規模農業の方が安価に作物を提供できるかもしれませんが、これは環境保護や食品安全性、供給の安定性確保にかかるコストを省いているためと言えるでしょう。
国際社会の一員として、私たちは大規模農業への過度な依存から脱却し、より持続可能な食料供給のあり方を模索すべき時期に来ています。
都市住民が変える未来:家庭菜園が拓く日本再生への道

食料自給率向上への道は、必ずしも大規模な家族農業だけに限りません。
都市住民による家庭菜園の普及も、日本再生の重要な鍵を握っています。
例えば、農業未経験の都市住民を対象に体験農園を提供している株式会社マイファームのような取り組みがあります。
マイファームでは、サラリーマンなどの本業を持つ人々に15平方メートルの土地を貸し出し、土づくりから収穫までインストラクターが丁寧に指導するサービスを提供しています。
多忙な時には、農作業の代行サービスまで利用できるため、気軽に家庭菜園を始めることができます。
無農薬で育てられた野菜を収穫し、「採ったその場で洗わずに食べてください」という指導のもと、参加者たちは「これが本物の野菜だったんだ」と感動を覚えると言います。
同社の試算では、6万人が体験農園を利用すれば、食料自給率が1%向上し、38万ヘクタールある耕作放棄地のうち2万ヘクタールが回復すると予測されています。
もし、このようなサービスを提供する企業が全国各地で多数誕生し、利用者数が20倍にまで増えたらどうでしょうか。
耕作地は40万ヘクタール増加し、耕作放棄地の問題は解消に向かうでしょう。
同時に、食料自給率は20%増加し、現在の38%から60%近くまで上昇する可能性を秘めています。
近い将来、少子化や人口の地方分散が進めば、都市部でも人口が減少し、空き地が増えることが予想されます。
これらを活用すれば、都会でも手軽に家庭菜園を楽しむことができるようになります。
かつての日本人は、小さな庭を持ち、緑と共に暮らすという自然との調和を大切にしてきました。
今後は、空き家を積極的に取り壊し、家庭菜園に転用することで、都市住民も緑に親しみ、災害時の食料供給源を確保することができます。
家庭菜園は、子供たちには情操教育を、大人には癒しを、そして高齢者には身体を動かすことによる健康増進をもたらしてくれます。
家族農業や家庭菜園を通じて、国民の健康増進、国土の豊かさの維持、そして食料輸入へのリスク軽減を実現できるのです。
まとめ
日本の食料安全保障は、超高齢化、食料自給率の低さ、耕作放棄地の増加、そして農業従事者の高齢化という複合的な課題に直面し、まさに「崩壊寸前」の危機に瀕しています。
安価な大量輸入に依存する現在の食料供給システムは、国内農業を疲弊させ、日本の食料自給能力を著しく低下させてきました。
しかし、この危機を乗り越えるための道筋は存在します。
国連が提唱する「家族農業の10年」が示すように、資源効率に優れ、持続可能な食料供給を可能にする家族農業の重要性は国際的にも認識されています。
そして、都市住民による家庭菜園の普及は、食料自給率の向上だけでなく、耕作放棄地の解消、地域の活性化、そして人々の心身の健康増進にも貢献する可能性を秘めています。
私たちは、単に「食料を買う」という消費のサイクルだけでなく、「食料を育てる」という生産のサイクルにも目を向けるべき時を迎えています。
家庭菜園に興味をお持ちの方は、ぜひ一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
日本の未来は、私たちの選択と行動にかかっています。
参考書籍⇒Renaissance vol.13 食がもたらす病













